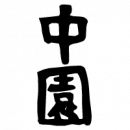学生時代、ぼくは友人3人とバンドを組んで活動していたのですが、その関係で大阪のアメ村にあるタトゥースタジオに出入りしていたことがありました。
そこで知り合ったひとつ年下の女の子と気が合い、付き合うことになったのです。ぼくにとっては初めての彼女でした。
初めての彼女
高校時代、男女数人ずつのグループで遊びに行くことはあったものの、特定の女性と付き合ったことなどなかったぼくは、大学に入ると、はやく彼女が欲しくてうずうずしていました。
当時はパソコンやスマホもなかったので、AVをレンタルしたり、たまに購入したりして毎夜オナニーにふけっていたものです。
街で綺麗な女性やスタイルのいい女性を見かけるとたまらなく興奮してしまい、そのときの映像を思い出しながらオナニーをすることもありました。
彼女が欲しいと思い過ぎるがあまり、危うくデート商法に引っ掛かりそうになったこともありました。
そんなときに出会ったのが、マキ(仮名)という名前の女の子でした。彼女は服飾系の専門学校に通いながらカラオケボックスでアルバイトをしていて、ぼくと出会った日、たまたま女友達に誘われてタトゥースタジオへ遊びに来ていたのでした。
ぽっちゃり体型の眠たそうな顔の女の子、というのがマキに対する第一印象でしたが、ぽっちゃり体型に見えたのは、どうやらぼくの錯覚のようでした。
彼女は小柄でしたが、胸が大きく太腿がむちっとしていたので、座っているとぽっちゃりしているように見えたのです。
マキとはその後も何度かタトゥースタジオで会う機会があり、バンドのメンバーと一緒に彼女のバイト先のカラオケボックスに遊びに行くようにもなりました。
ぼくたちが付き合い始めたのは、出会って2か月が過ぎた頃でした。
彼女の部屋で見たもの
その日もタトゥースタジオへ遊びに行っていました。ぼくなんかと同じようにバンド活動をしている仲間が普段から集まっていて、音楽やアートの話で盛り上がっていました。
どういうわけか、ここではエロい会話や下ネタ話をしているのを聞いたことがありませんでした。
マキは、彫師が客の女性に施術しているところを真剣な眼差しで見つめていました。
「もしかして、タトゥー入れようと思ってるん?」ぼくが聞くと、彼女は「うーん、まあ、考えてないわけじゃないよ」と、こっちを向かずにつぶやくような口調で言いました。
夕食にふたりでお好み焼きを食べに行きました。店を出たところでふと夜空を見上げると、綺麗な満月が出ていました。夜風がちょっと冷たく感じられるようになってきた10月半ばのことです。
「今からあたしの部屋来る?」
「え?行っていいの?」
「うん、いいよ、来て」
付き合い始めて3か月、ぼくは初めて彼女の部屋に入ることになったのでした。
マキの部屋には、学校で使っている服飾の本はもちろん、ファッション系の雑誌がたくさんありました。
音楽雑誌やCDもけっこういっぱい持ってるなぁと思って見ていると、その横に『BURST』が10冊くらい並んでいて、ちょっと驚きました。
『BURST』は当時、一部の愛好家たちのあいだで人気のあったサブカルチャー系の雑誌で、タトゥーやピアス、ドラッグ、死体写真、スカトロなどを扱った刺激の強い内容のものでした。
その過激な内容のおかげで2008年に有害図書に指定され、廃刊となりました。
タトゥースタジオの本棚にも置かれていて、ぼくも何度か読んだことがありましたが、なかなかのバッドテイストで刺激が強かったです。
タトゥーやピアス(皮膚の下に埋め込むピアス?)などによって全身を改造されたサイボーグみたいな女性の全裸写真なんかも掲載されていて、紙面に目が釘付けになることもあれば、そのグロテスクさに思わず目を背けてしまうこともありました。
そもそも当時の大阪のアメ村が、そういう雑誌で取り上げられるような雰囲気の街で、アウトローな人たちもたくさんいる危険な場所でしたから、タトゥースタジオで『BURST』を読んだ日には、帰り道に誰かに襲われやしないかビクビクしながら歩いたものです。
『BURST』の他にもサブカルチャー系雑誌が何冊か、彼女の部屋にはありました。マキがそんな雑誌を持っているのが意外でした。先ほどのタトゥースタジオでの発言も合わせてちょっと気になりました。
しかし、初めて彼女の部屋に来たという緊張感と、はやく彼女とエッチがしたいという興奮のほうが勝ってしまい、このときぼくは正直、居ても立っても居られない状態だったのです。
初エッチの記憶
その夜、ぼくは彼女とセックスをしました。ぼくにとっては初体験でしたが、それまでずっと思い描いていたような(AVで見るような)興奮度MAXな時間ではなく、すごくあっさりしたものでした。
もっとハァハァ言いながら腰を振り、彼女のほうも「あっ、ダメっ、イッちゃう!あぁぁん!」と喘ぎながら昇天し、終わった後もハァハア言いながら汗だくになって抱き合っている光景をイメージしていたのですが…。
実際はすごくサッパリしていて、事が終わった後ふたりとも平常心でベッドに横たわっていたような気がします。汗だくにもなっていませんでしたし、ハァハァ言ってもいませんでした。
ぼくが乳首を舐めたときと、ペニスを挿入した瞬間だけ彼女は「あぁっ…」と気持ちよさそうな声を漏らしましたが、それ以外では(お互いに)ほとんど声を出すこともなく、静かに事が進み、静かに事を終えた感じでした。
初エッチのときのことで、今でもはっきりとぼくの記憶に焼き付いている光景は2つ。
ひとつは、ぼくが知らないうちに彼女が枕の下にコンドームをこっそり忍ばせていて、タイミングを見計らってそれを取り出してきたこと(ぼくも自分で買って鞄の中に入れていたのですが)。
もうひとつは、服を脱いでベッドに腰かけた彼女が、片方の腕で胸を隠しながらそーっと布団の中へ入ってきたとき。そのときの彼女の恥じらう仕草と、胸のふくらみがたまらなくエロく感じられたこと。
その2つの光景だけは、25年経った今でも鮮明に覚えていて、それ以外の場面はぼんやりとしか記憶に残っていないのです。
初体験の3日後に、ぼくは彼女と2回目のセックスをしました。このとき調子に乗ったぼくは、たいした持続力もないのに、正常位の途中で体位を変えたいと彼女に言いました。
バックから挿入しようとした瞬間、ぼくは我慢できなくなって射精してしまいました。
挿入することなくフィニッシュしてしまったぼくを、彼女が不思議そうな顔で見つめていました。
持続力がなかったことよりも、彼女に無理を言ってこんな恥ずかしいポーズをとらせたことを恥ずかしく申し訳なく思いました。
その後も、ふたりで会うたびにセックスをしていたように思います。ぼくが一人暮らしをしていた京都のアパートに彼女が泊まりに来たこともありました。
いちどだけラブホテルへ行ったことがありました。『おとぼけビーバー』というアホっぽい名前のホテルでしたが、これがなかなか楽しくて、ぼくは満足できたのですが、彼女はどちらかというと自分の部屋で過ごすほうがよかったみたいです。
「あたし、彫師になる!」
年が明け、あっという間に次の春がやってきました。ぼくも彼女もそろそろ就職活動を始める時期になっていました。
この頃になって、ぼくはようやく携帯電話を持ち始めました。ガラケーなんていう呼び名もまだなかった当時の、アンテナを伸ばして使うタイプの携帯電話です。
マキは一足はやく携帯電話を使っていたので、これで互いの連絡手段が簡易化されて便利になりました。電話番号が書いてある手帳を持ってわざわざ電話ボックスまで行く必要がなくなりました。
ある日、ひとりでふらっとタトゥースタジオへ寄ってみると、女性彫師のリカさん(仮名=スタジオのオーナーTさんの妻)が女性客を施術中だったのですが、その女性客の顔を見て、ぼくは思わず「えっ、何してるん!?」と素っ頓狂な声を上げました。
今まさにタトゥーを彫ってもらっているその女性客がマキだったのです。とっさに、彼女の部屋にあった『BURST』のことを思い出しました。
「彼氏がびっくりしてるよー」リカさんが言いました。マキは何も答えず、施術台の上であおむけになって天井を見つめていました。
彼女の右の乳房が半分くらい露わになっていて、鎖骨の下あたりにグラデーションのかかった鮮やかなブルーで蝶の絵柄が描かれていくのを、ぼくはしばらくその場に立ったまま見つめていました。
「あたし、彫師になろうと思ってる」
施術が終わって一息ついたとき、彼女がそう言いました。
「ここで見習いとかするのん?」
「ううん、学校を卒業したら四国に行こうと思ってる。リカさんの師匠やった人が徳島でスタジオやってるんやけど、そこに修行に行くつもり」
「ふーん、そうなん…」
このとき、ぼくはマキと別れることになるのだろうと、漠然と考えました。まだ実感はありませんでしたが、頭でははっきりとわかっていました。
彼女のタトゥーの数は少しずつ増えていきました。
ふくらはぎや踵の辺りにも小さな模様やジグザグのラインが彫られていて、それらはマキが彫師のリカさんに教えてもらいながら自分で彫ったものだそうでした。
マキは専門学校を卒業すると、宣言していた通り徳島へと彫り師修行の旅に出ました。ぼくと出会う前から、彼女はすでに彫師になることを考えていたそうです。
「何年かかるかわからんけど、将来は自分のタトゥースタジオを開業したい」そう言って、彼女は旅立ちました。
あれから25年が経った現在、彼女がどこでどんな暮らしをしているのかはわかりませんが、きっと、どこかの街でタトゥースタジオを開いているのではないかと、ぼくは思っています。